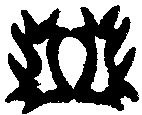
人魚謎お岩殺し
小栗虫太郎
|
今こそ、二三流の劇場を歩いているとはいえ、その昔、浅尾里虹の一座には、やはり小屋掛けの野天芝居時代があった。
それでこそ、その名は私たちの耳に、なかなか親しみ深くでもあり、よしんばあの惨劇が起らなかったにしろ、どうしてどうして忘れ去れるものではなかった。
と云うのは、その一座には、日本で一ヶ所と云ってもよい特殊な上演種目があった。それがほかならぬ、流血演劇だったのである。
そこで、一つ二つ例をあげて云うと、「東山桜荘子」の中では、非人の槍で脇腹を貫く仕掛などを見せ、夏祭の泥試合、伊勢音頭油屋の十人斬などはともかくとして、天下茶屋の元右衛門には、原本どおり肝を引き抜かせまでするのであるから、耳を覆い眼を塞がねばならぬような所作が公然と行われ、卑猥怪奇残忍を極めた場面が、それからそれへと、ひっきりなしに続いてゆくのだった。
さらにそれ以外にも、今どきとうてい見ることのできない、ケレンものなども上演されて、「小町桜」や「天竺徳兵衛韓噺」では、座頭の里虹が、目まぐるしい吹き換えを行い、はては、腹話術なども用いたというほどであるから、自然と観客は、血みどろの幻影にうかされてしまって、いつとなく、魔夢のような渇仰をこの一座に抱くようになった。
しかし、ここで奇異は、南北の四谷怪談であるが、それだけは、かつてこの一座の舞台に上ったためしがなかったのである。
事実作者も、幼少のころおい、この一座の絵看板には数回となく接していて、累や崇禅寺馬場の大石殺し、または、大蛇の毒気でつるつるになった文次郎の顔などが、当時の悪夢さながらに止められているのである。それゆえ、もしその当時に、お岩や伊右衛門はまだしものこと、せめて宅悦の顔にでも接していたならば、作者が童心にうけた傷は、さらにより以上深かったろうと思われる。
ところがついにそれは、小芝居にありきたりの、因果噺ではなかったのである。
寄席の高座で、がんどうの明りに、えごうく浮き出てくる妖怪の顔や、角帯をキュッとしごいて、赤児の泣き声を聴かせるといった躰の──そうしたユーモラスな怖ろしさではなかった。それとは、真実似てもつかぬ、血と人体形成の悲劇だったのである。
狂乱した肉慾が、神の定めも人の掟もあっけなく踏み越えて、ただひたすらに作り上げた傑作がこれであり、里虹一座の人たちは、まったく油地獄のそれのように、うちまく油流れる血、踏みのめらかし踏みすべらかして、とめどない足のぬめりに、底知れず堕ち込んで行くのだった。
そこで作者は、あの隠密の手のことを語りたいのである。
それには、宿命の糸を丹念にほぐし手繰り寄せて、終回の悲劇までを余さず記してゆかねばならぬのであるが、まず何より、順序として里虹の前身に触れ、あの驚くべき伝奇的な絡がりを明らかにしておきたいと思う。
今世紀のはじめ、ケルレル博士の発議によって、丁抹領リベー島に、犯罪者植民が行われた。またさらに、それから一、二世紀遡って、フリードリッヒ・ウイルヘルム一世の頃には、帝の異常な趣味から巨人の男女を婚せしめ、いわゆるポツダムの巨兵を作ろうとした。ところが、日本においても天明のころ、その二つを合したような、事蹟が残されているのだ。
それが紀州公姉川探鯨だったのである。
正史においてすら、仄かではあるけれど、西班牙との密貿易の嫌疑が記されているように、雄志禁じ難い不覊奔放の性格は、琉球列島の南毛多加良島の南々東に、ささやかな一珊瑚礁を発見した。そこに、かたわら体躯の優れた犯人男女を送って、いずれは近侍に適わしい、巨人育成法が試みられたのであった。
その島は夷岐戸島と名づけられて、嵐のあと、空気の冷たく身に堪えるころには、落日の縞を浴びて、毛多加良島からも遠望された。そのなかで、絶えず囚人たちは、慌しい気圧の変化や、小さな波を呑み尽してしまうような大波の出現、雷のような海底地震の轟き──などに気を打たれていたが、やがて、海の階調のすべてを知り尽くしてしまうと、静かに赦免の日を待つようになった──しかしそれは、彼らの次代に巨人を得た際のことである。
ところが、まもなくこの一孤島に、不思議な囚人が訪れることになった。
と云うのは探鯨の雅号が、無束というのでも分るように、彼にはまた、通人的な半面があって、ことに俳優を愛したのであった。けれども、結局にはそれが禍いとなって、あろうことか正室薄雪の方が、上方役者里虹と道ならぬ褄を重ねたのである。薄雪の方は、嵯峨二位卿の息女であり、一方は門閥もなく、七両の下廻りから叩き上げた千両役者なのであるが、ついにその二人は、島の外にある小島に隔てられて、凋んだ花の香りを、絶海の孤島から偲ぶ身になったのである。
しかし、この孤島の所在は、探鯨の死と同時に国替えなどもあって、ついに姉川家の記録から、消え失せてしまったのであった。
ところが、それから何十年経った後のことだったろうか、はからずも流島のさい実家に送った文書が嵯峨家から発見されて、ようやく惨鼻を極めた流島史が陽の目を見ることになった。
と云うのが、明治廿一年三月のこと──嵯峨家の当主は、そのおり快走艇に乗じて日本に廻航した、著名な生理学者ベルナルド・デ・クイロス教授に打ち明けて、帰途その孤島に、立ち寄られんことを懇願したのであったが、どうしたことか、その後ハノーヴァーに移った教授からは、なんの音沙汰もなく、そうして人移り星変るうちに、いつとはなく忘れ去られてしまったのであった。
ところが、今年になって、はしなくもその孤島にまつわる、秘密が曝露されたと云うのは、教授の遺品として、一通の文書と油絵とが送られて来たからだった。
作者は、次行にその全文を掲げて、この事件の発端を終りたいと思う。
──一八八七年四月十七日日没間近の頃、余は嵯峨家の依頼によって、北緯二十七度六分東経百三十度五分の海上を彷徨した。
しかして、夷岐戸島の姿を遠望するに及んで、余はまったく度肝を抜かれた。珊瑚礁の奇観も、ここに至っては、海に根を張って空に開いた、大花弁というほかにないであろう。その赤紫色の塊団は、さながら和蘭風の刈籬を想像させた。島影は、落日のため硫黄色に焼け爛れて、真直な一条の光線が、中央にある小丘の上に突き刺っていた。
微風は、椰子花の匂いを混ぜた海の香りを、余に向ってまともに吹きつけた。
しかし、そうしているうちに、ふと余の瞳に映じたものがあって、その衝動の苛烈さには、思わず双眼鏡を取り落したほどだった。
それから余は、狂わんばかりに夢中になり、その双眼鏡を、かわるがわる船員に貸し与えたのであったが、いずれも血の気を失った。
余は幼少のころ、霧深い大気の中で、樹木を妖怪と信じたこともあったが、この場合は断じてそうではない。しだいに余の魂は、現実に戻るのを嫌うようになった。そして、ある詩の一句を口誦みながら、ひたすら幻想の悦楽に浸っていたのである──それは、眼前の渚に遊ぶ一個の人魚を見たからであった。
上半身は、それは美しい女体であるけれども、腰から下は暗い群青色に照り輝いて、細っそりと纏った足首の先には、やはり伝説どおりの尾鰭があった。
彼女は、猫のような優やかさで動いてゆき、身を差し伸べるときには藻草のような髪が垂れ、それが岩礁の中で、果物の中の葉のように蒼々と見えた。
そこで余は、さっそく島に向ったが、暗礁多く、上陸したのは翌朝だった。
ところが、意外のことに、人魚は一夜のうちに何処かへ消え失せ、余は二人の日本青年と、これも嬰児を二人拾い上げたにすぎなかった。
そこで、島を離れ、ミンダナオ島に向うことになったが、その夕べ、悪夢は再び繞り来った。今度は、生々しい現実の恐怖を味わねばならなかったのである。
それは、翌夕日没直後のことで、なにか鑵鼓のようなもので、舷側を叩く音がしたので、余は暗闇の海中に絞盤を下ろさしめた。
すると、その巨大な網は、金色の滴を跳ね飛ばしながら、徐々と闇の深みから現われてきた。しかしその瞬間、余は巨大な力に、ギュッと心臓を掴まれたような気がした。
それは、板戸のような栰であったが、表面には、まだ呼吸のある、二人の嬰児が結わい付けられてあった。ところが、裏面を返してみると、そこにあったのは、首も手足もない、年若い女の胴体だったのである。
余は、その際の光景を、未だに想起することができる。
月のない海には、赤い光がどんよりと映り、女の屍体からは、液体の宝玉がしずくのように滴り落ちている。
それは、女の乳房を、豪奢な王冠に変えたかのようで、中央の乳首には、夜光虫が巨大な金剛石となって輝き、ぐるりの妊娠粒には、いちいち光る滴が星をふり撒いているのだ。そうして、この陰惨な場面が、どれほど華やかなものにされていたことだったろうか。
しかし、余らはまもなく意識を取り戻し、女体を水葬した後に、出帆したが、わけても困らされたのは、二人の日本青年に言語が通じないということだった。
しかし、そのうち一人が、アサオリコウという言葉を、しきりに口していたのを記憶しているが、何より四人の子が、二人のいずれに属するものか不明だった。その後余は、ルスン島の土人港バグアイにおいて、以上の六人──すなわち青年二人男児三人女児一人を、本国に送還したのであったが、その間目撃した異常な秘密については、今でさえも狂わんばかりに夢中である。
それがあるいは、超自然的な要素であるか、それとも夢と本質を同じうしているのか、あるいは単に、余ら乗組員の全部が、神経の病的な亢奮に陥っていたのであろうか。
しかし、その驚くべき神秘については、余に語るべき舌はない。
別送の一幅に含ませて、その謎を嵯峨家に奉呈するものである。
以上のとおり読み終ると、法水麟太郎は眼前の里虹を見た。彼は今日、めずらしく渋い服装をしている。
七つ糸の唐桟の対に、献上博多の帯をしめた彼を見ては、黒死館における面影など、何処にも見出されないのである。それは、彼自身にも俳優の経験があるばかりでなく、特殊演劇保存という見地からして、この一座とは何かと親しかった。
そこは、武州草加の芝居小屋、年も押し迫った暮の廿八日のこと──。
はや春興行に、乗り込みまでも済ました一座のものは、薄汚い仕度部屋のなかで、車座になっていた。
ぐるりには大入袋や安っぽい石版摺りの似顔絵などが、一面に張られていて、壁地の花模様などは、何が何やら判らないほどに、色褪めていた。
すべてが、腐った沼水にうつる水際のように、なんともいえぬ陰気な代物ばかりだったのである。
「どうだね真鳥屋、これには覚えがあるだろうが」
法水にそう云われて、里虹は慇懃に頷いた。彼は、懐古とも怖れともつかぬ異様な表情をして、凝っと伏目になっていた。
年のころは、六十を幾つか越えていて、牡牛のような、がっしりと肥えた多血質の身体をしていた。おまけに、台詞以外には吃る癖もあり、かつは永らくの阿片吸飲者でもあって、皮膚にはどこか薄気味悪い──まるで象皮腫のそれのような浮腫が一面に拡がっているのだった。
しかし、彼が孤島から救われた一人であることは、ここで贅言を費やすまでもないことだろう。
やがて法水は、側の壁に視線を転じ、そこに立て掛けてある絵を見入りはじめた。
それは百号ほどのもので、数世紀も遡行したと思われるような、暗い色調で描かれていた。事実クイロス教授が持ち出した謎は、この画中において、さらに混沌たるものになってしまったのである。
しかし、特徴と云えば二つほどあって、一人が蒼ざめ、打ち伏して苦悶していると、もう一人は、これは右胸を押え同じような表情をしている。
また、もう一つは、二人とも指の節が太く、髪の毛が薄く、頭が水頭のように膨れあがっていることだった。
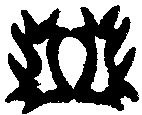
しかし、以上のほかに、もう一つ際立って不思議なものがあったのである。と云うのは、二人とも、双方の足首に上図のような紋様が描かれ、それは──あるいは捺されたと云ったほうが、適切であるかもしれない。
「どうも僕には、クイロス教授の意志というのが、判らんのだがね。しかし、こう離れて見ていると、なんだか怖ろしいような気がしてくるじゃないか。どうやら、ボルルワスキーかニコラス・フェリー──臭いのだが……」
あるいは、朱と暗緑の対比から、発しているのかもしれないが、事実その絵からは、竦ませるような鬼気が迫って来るのだ。
法水は、なにやら云いたげな顔をしたが、その時隅から中山小六が乗り出して来た。
この老人は、耳の辺まで垂れた白毛を残して、てかてかに禿げ上っているが、身体は十一、二の子供くらい──どこからどこまでが、典型的な侏儒だったのである。しかも、どことなく弱々しく、腰も曲りかけている。
小六は半畳ほどずり出して、狡そうな笑を泛べ、
「すると、なんですかな先生。いまおっしゃった異人の名というのが、なにかこの図紋とでも関係がござんすので……」
と云うと、相手の深々とした皺を、法水は、痛ましげに見やっていたが、
「いやいや、なんでもないのだよ。じつは、ちょっと他のものに、附会けていたんだがね」
と何げなく云ったけれども、その眼はただならぬ暗色を湛え、ギロリと六人の車座を見まわした。
明敏な読者諸君は、すでに気付かれたことと思うが、小六はさておき、里虹を交えた他の四人というのが、その年配といい、なにかしら夷岐戸島の四人の嬰児を想い起させるではないか。
しかし、その暗合の魔力は、ついにその場限りではなかった。その時法水は、ただそれらしい符合に打たれただけで、やがて心火にめぐりはじめる、片輪車のことなどは毛ほども知らなかったのである。
法水が帰ってからも、一座はそのままの沈黙を続けていた。
霜刻に近い夜ふけの楽屋の中は、いたって火の気も乏しく、外の凍りが室内にも及んで、幟のはためきに、歯の音も合わぬほどの寒さだった。
そのうち山村儀右衛門が、例の神経的な、蒼白いしゃくれ顔を突き出して、
「ところで爺つぁん、春にはなんとかして当てようと思うんだがね。いっそ、慣例を打ち破って、四谷をやってみたら、どんなものだろう。伊右衛門はわっし、お岩は逢痴と、配役はざっとこんなもんでさあ」
と云って、彼はかたわらの逢痴と顔を見合せるのだった。
逢痴は、一座中の若女形だった。寒さにもめげず、衣紋を抜き出して、綺麗な襟足を隠そうともしない。
この逢痴には、はじめ二つの世界があった。
一つは、楽屋における男性であり、一つは、舞台における女性であったが、やがて自働的な聯想を起したのであろうか、今ではもう、感情挙動言葉服装とも、女性のそれと異ならないものになってしまった。
まったく着物のままざんぷりと水に漬けて、どこからどこまで透き徹してしまっても、たぶん彼には、女性以外の特徴が見出されないに相違ない。そうして、古風な芝居言葉だが、お内儀様と云われるのを喜んだり、箸の持ち運び、食事の仕様までもそのままなのを見ると、それが山下久米八と、いかに際立った対照をなしているか判ることと思う。
久米八は、他の三人と同じ、四十を超えた老女優だが、肉のかたく引き緊った、どこかに厭味のある顔立だった。
彼女は、すべてが男性化していて、その汚なげによごれた爪にも、身嗜みのないことを証拠立てている。
そして、その三人に挾まって、なんら特徴のないのが村次郎だった。
寡黙な、芸の引き立たないこの男は、容貌にも特徴がなく、いつも髪の毛に埃っぽい匂いがする──とまあそういったような、何から何まで役者らしくない男だった。
しかし、里虹はそう云われると、半白眼をぴたりと、儀右衛門に据えて、
「四谷……。へん、めっそうもねえ」
と吐き出すように云い放って、
「のう友田屋、おぬしは法水先生のお気に入りで、えらあく学問にも身を入れたものだが、新劇とやらはいざ知らず、この一座には四谷は北向きなのさ」
と壁に貼り付けてある写楽の絵で、岩井喜代太郎が扮している、「関本おてる」の色刷を見て、
「だいぶ安手な写楽のようだが、聴くところだと、喜代太郎はそれほどの背高じゃねえというそうだぜ。ただ写楽が、煙管を長く描いたもんだから、後々のうるさがりやが、高い背丈と釣合いの煙管なんて、そんなことを吐ざいたそうなんだよ。喜代太郎が、どうして高えもんかな」
と、話を外らすような、しかも、異様な言葉を口にしたのだった。
しかし、そう云いながら、里虹はぜいぜいと息を切らし、顳顬の脈管が、蛇のように膨れ上っているのが見えた。
彼はしばらく硝子戸越しに、外ではためいている幟を見詰めていたが、やがて返した眼が配役の一部に触れると、
「いいから、窓でも締めねえってことさ。こうして、車座になっていると、うっかり丁半とでも間違われるわな。おう、だいぶ風が出たのう。だが、吹いてるからいいようなものの、これが収まりゃ、そりゃ事だぜ」
と、異様な言を吐き嘲ら笑いながら、彼はつと立ち上ってしまったのである。
その夜儀右衛門は、いつまでも寝つくことができなかった。閉め忘れた裏木戸が、風のためにバタンバタンと鳴りつづけ、大道を吹き荒ぶ風は、松飾りに浪のような音を立てさせている。ふと、その響きに、彼は夷岐戸島の海鳴りを聯想したのである。
──はじめ想い泛べたのは、数字の符合だった。それは、夷岐戸島における四人が、現在自分をはじめの四人ではなかったかということだが、クイロス教授の文書を見ても、それには三男一女という符合があり、もはや疑うべくもないのだった。
さらに、もう一つの証拠というのは、四人がいずれも、実の父母を知らないということで、戸籍面を見ても、一家を創立した戸主になっているのだ。
そして、いまはっきりと知ったのは、四人のいずれか二人が里虹を父にしているということ──それが島中の二人が、島に流された二人であるか。また里虹の子以外の二人は、いったい誰を父にしているのであろうか。
その疑惑の深さには、現実も幻も差別がなく、揉み込めば揉み込むほど、頭の中に触れる突起がなくなってしまって、やがて彼は恍惚となってしまうのだった。
しかし、そうしているうちに、ふと松飾りのざわめきに触れると、彼の神経はふたたび鋭くなってきた。
そうして、今度は夷岐戸島に行き、不思議な人魚の行衛は、女の惨屍体は──と繞らせているうちに、いつとなく島内における、祖父母たちの生活を想い起すのだった。
──あの島における祖先の次の時代に、もし男の子と女の子とが、生れたとしよう。するとそこには、道徳も思想も、言語も抑制もあり得ないはずである。
ソドムの崩壊の日、生き残った一人の父と二人の娘は、いったいなにを行なったか。それは抱擁であり、肉慾であり、大いなる沈黙の儀式である──種族保存のためには、あの刑罰の神、エホバですらもそれを許したではないか。
しかし、近親相姦は……
儀右衛門はそこでハッとなり、鋭い苦痛を思って、慄え戦いた。彼は夜具に触れる衣擦れにも、獣めいた熱っぽさを覚えるのだった。
と云うのは、二人とも二十まえのことであったが、ふとした魔の戯れから、一夜山下久米八を犯してしまったのであるから。しかし当時の記憶といっても、声も立てない、まるで年増のような子供だったということや、その時逃げ出した足の下で、石ころが気味悪くごろごろしていたということなどで、それすらも、今では懲罰の意味を持つようになってしまった。
もしやして、二人が兄妹だったら──と。
いきなり血のさわぎを覚えて、儀右衛門は吾となく、胸をかきむしった。氷のような悪寒が脊髄を貫き走った。
彼は自分の血管の中に、木を噛む虫のような音を聴いたのである。その途端、儀右衛門は強烈な衝動に駆られて、一目散に楽屋のなかへ、飛び込んで行ったのであった。
そして、永いこと薄闇のなかに立ちつくして、彼は油絵具の、どんよりとした反映を見詰めていた。
が、心の中は、里虹に対する憤りで一杯だった。
あの男が、自分の父親であるかないかはしばらくさておき、もしそうでないとして、戸籍面をあのようにしたとすれば、とりもなおさず、自分が経験した近親相姦の悩みを、他の子供たちにもなめさせようとしたのではないか。
また、事実自分の子であったとしても、そういった悪魔的な性格は、あの男に必ずやあるに相違ない。
わけても、苦悩が酷烈なそれだけに、その心理はあながち奇蹟とは云われないはずである。それにしても、この四人ははたして誰の子なのであろう。一人、二人、三人、四人──そのうち二人が、たしかに里虹の子にはちがいないのであるが……
と、1、2、3、4──と数字の幻像が目まぐるしく駈け廻っているうちに、いかなる心理的な結合であろうか、いきなり6と9の上に、強いスポットのような光が落ちた。そして、その瞬間、儀右衛門は髪の毛が動いたかと思った。
何故なら、6と9と組み合わせた形は、胎内における双胎児のそれではないか。まったく、身も世もないあの烈しい相剋のなかで、静かに天鵞絨のうえを滑ってゆく思考の車があったのだ──それに今まで彼は気づかなかったまでのことである。
すると、五感が異常にするどくなって、まもなく儀右衛門は、画中から驚くべき特徴をつかみ出した。
それは、双生児にはつきものの鏡像なのであった。
鏡像と云えば、おおかた読者は承知のことであろうが、左と右、右と左といった具合に、双生児の各半面が相手の反対側に酷似することである。
画中では、それが頭の渦にも、利手にも顔の歪みにもあったので、はっきりと儀右衛門は、最終の解答を掴んだように感じた。
四人のうち二人は、たしかに双生児でなければならない──しかし、それを自分の身に及ぼしてみると、いまや儀右衛門は、世界中の嘲りを一身にうけているような気がした。しかしそれには、氷でも踏んでいるような、鬱然とした危懼さがまたあって、まだ何かありはしないか、ありはしないかと、全身の毛が一本一本逆立ってゆくような焦だたしさを覚えてくると、はしなく眼に止まったのは、畳の上に置かれ放しになっている、配役書だったのである。
で、窓を開けると、乳色の清々しい月の光が差し込んできて、その刹那、彼の眼をハッシと射返したものがあった。
直助権兵衛──その名を儀右衛門は、なぜか妙にひしむような、闇の香りのなかで味いはじめた。
それは、はじめ儀右衛門が、配役書きを置いたとき表に出た部分であって、里虹は一瞥をくれたのみ取り上げようともしなかったのであるが、しかしそれには、はっきりと彼の嘲りが泛び出ていた。
直助、権兵衛と──そう二つの名が重なり合っていることは、おそらく里虹のみが知る双生児の表象であろうし、さらに、実の妹とも知らずお袖と懇ろにした、骨肉相姦の意味も必ずやあるに相違ない。そうして、刻々と血が失われてゆくような真蒼な顔をしながら儀右衛門はじっと闇の中に立ちつくしていた。が、そうしているうちに、ふと彼の心を訪れてきた仄白い光があった。と云うのは、直助権兵衛と書かれたその下には、その役の嵐村次郎の名が認められてあったからだ。
村次郎、村次郎が直助権兵衛では、お袖は──と、やにわに彼はその全文を拡げてしまった。そして今や、動かぬ証拠を、掴み上げてしまったのである。
直助権兵衛 嵐村次郎
お岩妹お袖 山下久米八
それは、綾にからまっている絆を、ようやく解きほどいたという感じだった。倦怠いような、銷沈いような、頭の血がすっと下ったという感じで、まるで夢見るような気持で、彼は手に持った二つの名を、ぼんやりと見詰めているのだ。
あの時里虹が、村次郎の名を見ただけで、キッパリと云い切った──というのも、また彼が、問わず語らずに暗示した不倫な関係も、ことごとく、二つの名のうちに秘められているのではないか。
村次郎と久米八は、明白に双生児であり、二人はそうとは知らず、直助とお袖が堕ち込んだ、鬼畜の道を辿りつつあるのだ。そう判ると、かすかな嫉妬を覚えたけれども、これまでの惨苦も懊悩も一時に消え失せて、残った白紙の眩ゆさには、何もかも忘れ果ててしまうのだった。
そうして、再び床に入ったけれども、裏木戸の音は依然として止まず、その間を逢って、雨の滴が思い出したように落ちてくるのだ。
それには心動のような律動があって、四人の胸近くにいる思いがした。
誰しも今夜は、見知らぬ父母に憧れて、母の乳首の勃まり、厚い脂肪の底から伝わる、軟らかな脈打ちの音に、眠らぬ一夜を過すにちがいないと思った。しかし、それには鬱然としたものが感ぜられて、なんとなくモヤモヤとした、いつかは犯罪とでもなりそうな、やがては夷岐戸島の秘密を中心にこの一座に起るであろう、自壊作用の兆ででもあるかに考えられるのだった。
ところが、どうしたことか、その夜のうちに予感が適中してしまった。
翌暁風がおさまると同時に、それなり里虹の姿が、掻き消えてしまったのであるから……。
「まあ聴きねえ。座頭がわっしのことを、新劇崩れと云うだろうが、一時この座を離れて、妙な銭にもならねえ、真似をやっていたことがある」
里虹の行衛が知れなくなって何月目か後のこと、警察でも尋ねあぐんで、結局不入りのための失踪ということでケリをつけたのだが、その日、先夜の四人を前に儀右衛門が切りだした。
「ところが、そのうち一番うけたのが、例の『椿姫』ってやつさ。いいから、わっしに喋らせねえってことよ。そこで、なかの濡れ場にだが、こういう台詞があるのだ。椿姫が、色男のアルマンの胸に椿の花を挿して、『今度はいつ逢いましょう』と云われると、『この花の凋むときに』と答えるんだが、わっしのやった芝居では、すぐ花を凋ませて、アルマンがやって来るのさ」
と、なにやら険しい気組で、儀右衛門はギロリと一座を見廻すのだったが、その比喩にぴたりとくるのが、いつぞやの夜、里虹が口にした──風が収まりゃことだぜ──と云った言葉だった。
それが、この事件にとると、秘密の中の秘密といったようで、妙に青黒い、底知れぬ池を覗き込むような気がするのだった。
けれども、一座の者はいっこうにさりげなく、この鋭い比喩に動じたような者もないのだった。
しかし、儀右衛門の心の中は、嵐村次郎に対する疑惑で一杯だった。ああも、ギスリと里虹に刺されたのであるし、よしんば彼が父であるにしろないにしろ、そうと知られた上は、口を覆うよりも針を立てよ──ではないか。
しかし村次郎は、相も変らず黙々としているので、その物静けさには一種不気味な気持に駆られる場合さえあった。
もしあの夜、楽屋に入った儀右衛門を、村次郎が知っていたとすれば、思うに自分は燃えさかる熱蝋を胸に突きつけられて掴もうにも由なく、足を引きながらたあいなく後ずさりして、一滴一滴と、手から腕にまた胸に、憐れな蝋涙をうけていかなければならぬのではないか。
そうして、朧気に迫ってくる恐怖に、ひしと悶えて日を送るうちに、いよいよ法水の肝入りで、一座の東都初登場となった。
その乗り込みの前夜、はからずも事件の神秘を、一つ解くことができた──それは、風が収まればと云った、里虹の謎なのであった。
そこは、上州藤岡の劇場で、乗り込みを両三日中に控え、ちょうど千秋楽の日であったが、儀右衛門はひさかたぶりに、法水の来訪をうけた。
舞台裏には、唐人殺しに使う、提琴や矢筒などが、ところ狭く散らばっていて、開場前の劇場は、空間がなんとなく物侘びしげであった。
ところが、しばらく見ぬ間に、儀右衛門は見る影もなくやつれ果て、青々とした剃り跡が、ひときわ目立っていた。法水の眼には、それが雲母を地にした写楽の大首か、それとも、何かの死絵のように見えた。
彼は、儀右衛門の頭が上らぬ間に、早々切り出した。
「手紙はたびたび貰っているが、君はあまり考え過ぎると思うね。だいたい自問自答というやつは、自分で自分の心を解釈するんだから、いつも標準が狂いがちなものなんだよ。だから、対象となる自分の心の状態が、どうも誇張されやすいのだ。ところで、しばらく来ない間に、だいぶ顔触れが変ったようだが……」
「ええ、最近に仮髪師を一人拾いましてな。ちょっとした端役もやりますんで、それに、浅尾為十郎という、ど偉え名をくっつけましたんですが……」
と儀右衛門に云われて、思い出したのであるが、楽屋口に入ろうとしたとき、一人の瘠せた老人を見たのを思い出した。その老人は、異様に皺が深く、ことに青磁色をした、珍しい皮膚の色が印象的だった。
儀右衛門は膝を組み直して、
「ところで、たびたび申し上げました、村次郎のことでござんすが、座頭の行衛について、一度ぜひお耳に入れたいことがございますので」
と云いかけたのを、慌てて遮って、
「君は、あまりに考え過ぎるんだよ。無暗に解剖をしたがるんだ。正直に云うと、里虹の事件よりも、自分の解剖の方が、面白いんじゃないかね」
と微笑んだ法水の眼には、儀右衛門の意外な変り方が映った。それは、懸命に唇を噛んで、なにかの激奮を耐えているかに見えた。
「その村次郎のこってすが、わっしゃほんとうに、済まねえことをしてしまったんで。かねて先生から、役の性根や心理の解釈に、いろいろと教えていただきましたが、それが今度という今度は、わっしにゃ恨めしいんで……。じつは久米八の兄妹は村次郎ではなく、やはり、このわっしだったのです」
と彼は、思いもつかぬもの静かな態度で語りはじめた。
「ねえ先生、聴いておくんなさい。いつだったか知らねえが、人間っていうやつは、自分の心の動きをなにかの図や、線や角などで表わしたがるという話を伺いましたが、それが、あの晩の里虹に現われたのです。
あの時窓の外を見て、風にはためいている幟をしばらく眼に止めていましたが、その後で、吹いているからいいようなものの、風が収まりゃ事だぜ──と云ったものです。
ところが、あの翌朝、風が収まると姿が見えなくなったのですから、どうもその暗合にわっしたちは不思議な魔力があるのではないかと、考えるようになりました。そして、磁石にでも引かれるように、その人間放れのした蠱惑に、ぐいぐいと引かれていったのです。
ところが、どうだったでしょう。ふとした事から、その時の黙劇じみた秘密を知ることができたのです。
あながちそれは、徴候発作なんていう、難しい言葉で云い表わさなくても、わっしたちのやくざ世界にだって、面白い逸話があるのですよ。
それは、いかさま札の名人と云われた並木可次郎なんですけど、なんでも勝負の終り頃になって、坊主の二十で勝負が決まるような局面になったのですが、もちろん可次郎にはその札はないので、むしろ自暴気味だったのでしょう。しかし、彼は凝っと考えて、一人に、いま何時だと訊ねました。すると、その一人がふと二つある時計のうち、円い方に眼をやったのを見ると、そこで可次郎は、ポンと札を卓上に投げ捨て、君が勝ったと、その一人を指摘したという話があります。なぜなら、手近の角形のものを見ないで、わざわざ遠い丸形のを見たとすれば、それは坊主の二十を持っている証拠としきゃ思われないじゃありませんか。
そこで先生、あの時里虹の前には、四谷の配役の中で、直助権兵衛(嵐村次郎)とあるところが、開かれてあったのですが、その前にたしか村次郎の幟を見たのでしょう。
だいたい幟というやつは、風に吹かれると、よくどこかに大きな皺ができて、文字の扁がなくなったり、はなはだしい時には、一字丸ごと埋まってしまうような場合もあるのですが、一つ試しに、嵐村次郎とある上半分から、風という字を除って御覧なさいまし。
それが山村となるではございませんか。
ねえ先生、やはりあの鬼畜は、わっしだったのですよ。そして、座頭が云った風云々という言葉は、暗に私たちの関係を嘲ら笑ったものなんです」
「なるほど、フロイドの全集の中には、家(Haus)というところを、心中考えていたことを露き出して、腰巻(Hose)と発音したり、また、死(Tod)と心の中に思っていた言葉が、逸話(Anecdote)を Anectode と書き誤らせた記述があるからね。しかし、君の分析は素晴らしいと思うよ」
と法水は、別にこれという感情を表わさなかった。
しかし、山村儀右衛門の解釈は、いまや驚くべき悲劇的な光景となって、彼の前に現われた──あの嫌厭すべき近親相姦者は、ついに彼だったのである。
儀右衛門は、ぶるぶる総身を慄わせて、自分の両手を厭わしげに見やっていたが、やがて言葉を次いだ。
「それから先生、またあの時里虹は、写楽の『関本おてる』を見て、事実喜代太郎はさほど背の高い俳優ではなかったのだが、誤って写楽が、煙管を長く描いたので、その釣合から、後世の鑑賞家が背の高い俳優と信じてしまった──と云ったのです。
しかし、これは、いわゆる比例の問題ではないでしょうか。
それに、贅言は要りますまいが、偶然わっしはその真相を知ったばかりに、夷岐戸島の秘密の一部を窺うことができたのです。
と云うのは、外界に対照するものがなければ、汽車でも汽船でも速度が判らないように、里虹はあの島で、もう一人の男ばかりを見ていたために、自分を巨人と信じてしまったのでした。そうなると、相手の一人が、恐ろしく背の低い男にならねばなりませんが、私は、いまだに身柄の不明な、中村小六がそうではないかと思うのです。あの侏儒だけが、自分以外唯一の大人だったので、里虹は自分を素晴らしい巨人と信じ、船影を望むに及んで、自分の妻と二人の双生子を葬ろうとしたのです。
と云うのは、私たちが、いわゆる男と女の畜生児だったからです。
しかし、その双生子はさておいて、どうして自分の妻を殺さねばならなかったのでしょうか。
いいえ、ここまで云えば、私と久米八とが双生子の兄妹だったということも、また往時の慣習からして、双生児の畜生児は殺さねばならなかったということも、さらに里虹が両親からの云い伝えで、クイロスの船を赦免船と信じてしまったことも……。つまり、わっしたちに関することだけは、けっして独断でもなく、またわっしの詮索が、度過ぎたのでもないことはお分りでございましょう。
けれども、問題なのは、里虹の妻が、そもそも誰であるかということです。そこで、一つクイロスの文書を、最初から思い泛べていただきたいですがね」
法水は、この時、眼前の儀右衛門が、精神の昂揚状態に入っているのではないかと疑った。
いろいろな影像が入れ代り立ち代り、驚くべきほどの早さで、相手の表情の中を、かすめ行くのを見た。
儀右衛門は、なにかしら怖ろしい力に、捉えられたかのように息をせき喘いで、
「ねえ先生、たしかクイロスの文書の中には、あの不思議な神秘的な生物──人魚のことが記されてありましたっけね。ところが、上陸するとその姿は見えず、その夜上った栰の裏側には、胴体だけの女の屍体がくくりつけてあったというじゃありませんか。里虹は、赦免の条件をあまり周到に考え過ぎた結果、この世にないもの、厭わしい一切のものを、自分の身近から葬り去ろうとしたのです」
「なるほど明察だ。とんとあの栰の趣向は、戸板がえしそっくりだからね。これで、里虹が『四谷怪談』を、本気で禁めていたという理由が分ったよ」
と云った法水の声も、耳に入らないかのよう、儀右衛門は気味悪げな、薄笑いを浮べて云った。
「さすが、先生だけにお察しは早えが、なによりわっしが知りてえのは、お母ろのことなんですよ。
人魚の首と、腰からしたをぶった切ってしまえば、それはただの首無し女にすぎねえじゃありませんか。
わっしは、上陸したクイロスはじめの人たちを見て、さぞ里虹が魂消ただろうと──実際首丈ほどもねえ大男なんて、この世の何処にあろうもんかな。
それから先生、近頃じゃわっしも、臥床に入ると、爪先から脈の音が聴えるようになりましたが、そうするとお母ろが、毛孔から海の匂いを吹き入れてくれて、すっかり雲のように、わっしを包んでくれるんですよ」
それは狂気の合間合間に現われる、綺びやかな夢幻のようなものだった。
いわば、それまで厭わしさに充ちていた現実の一部が、ここではっきりと、魅力あるお伽噺に変えられた。儀右衛門は、そうと知って以来母なる人魚に、それはわななくような、憧れを抱きはじめたのである。
おりおり母は、軟体動物が潜り込んでいる、割目を覗き込んで、無残にも軟らかな肢を引きちぎったり、あるいは苔の上を、滑べるようにして岩礁を乗り越え、噴き水を避ける時には、たぶん銀の腮や、貝殻のような耳が、チカチカと鈴のように鳴ったことであろう。
こうして、はしなくも儀右衛門が、幻影の世界に浸りはじめると、彼は別人のような気がして、一段と高い生活に上ったように考えられた。
まったく、その夢の最高頂においては、あの厭わしい現実の苦悶と拮抗できるのであった。しかし、一方において彼は、その人魚の形が、両肢の癒合した一本肢という、一種の畸形であることも熟知しているのだけれど、それとて、彼の夢を妨げる何ものでもなかったのである。
おそらく、そうでもしなければ、彼の心は均衡を失って、たちまち狂いの、どん底に叩き込まれたであろうが、そうして一方では、身も世もあらぬ悩みに悶え、また片方では、朦朧とした夢を楽しんで、からくも彼は、狂気の瀬戸際で踏み止まることができたのであった。
すると、儀右衛門に不思議な心理が起りはじめた。
と云うのは、考えても考えきれぬような異様な撞着ではあるけれども、そうして、人魚に伝説の衣を着せ、美しい霧一重に隔てて眺めはじめてからというものは、どうしたことかそれまで軽い愛着を覚えていた、久米八に対する情が消え失せて、さらにしぶとい、燃えさかるようなそれを、今度は逢痴に求めるようになってしまった。
それが、自然の本性に反した、不倫な慾求であることは云うまでもない。さらにまた、一種の心理的畸形とでも云えるだろうが、しかし、畸形はけっして奇蹟ではないのである。
いつとなく、儀右衛門の心を、あの聴くだに厭わしい、骨肉愛の悩みが蝕んでしまったからだ。それが、クラフト・エーヴィング教授の云うように、美しい母を持った者は、美しい女性に対して、驚くべきほどプラトニックであるとすれば、とりもなおさず儀右衛門のそれは、一種の女性恐怖にほかならないであろう。
彼は、そうした悪夢の中を漂い、人間に与えられた地獄味の中で、わけても、味のもっとも熾烈な、一つを味いつづけていたのである。
やがて、永い沈黙の後に、法水が口を開いた。
「しかし友田屋、これは、少し無理かもしれないがね。人魚も骨肉相姦も、当分のうちは、神話の中に収っておいたら、どんなものだろう」
と云って、儀右衛門がもじもじしているうちに、何を思いついたか、法水の表情が、いきなり硬くなった。
「ところで、もう一つ訊きたいのは、いまの君の考えだが、それを最近思いついたのならいいがね。もしあの晩だとすると、君が里虹を殺したといっても、けっして心理的に不自然ではないのだ」
「それは、同時に久米八もでしょう」
と透き通ったような蒼白い顔を、ピタリと据えて、
「わっしは、ただこれきりしきゃ知らねえのですよ。あの晩、風が止んだのが暁方の三時で、姿が見えないと騒ぎだしたのは、たしか六時十五分前頃だったでしょう。ですが先生、わっしにはなんとなく里虹が、この劇場にまだ、いるんじゃねえかという気がしてならねえのですがね」
そうして、なぜ──と反問したげな法水の顔を見るでもなく、儀右衛門は懐中から、一枚の紙片を取り出した。
それには、思わずも釘付けするような力があったと云うのは、いつぞやクイロスの画中、双生児の足首に捺されてあった異様な図紋の下に、次の文章が記されてあったからだ。
儀右衛門は役どころではなし、里虹を尋ねて、伊右衛門を演ぜしめよ。
「ところが先生、こいつがどう見えても、里虹の筆蹟に違えねえのですがね。それに、いま始めて判りましたが、どう考えたって、この図紋の形は、六本趾を二つ合わせたようで、夷岐戸島にいた、人魚の尾鰭のようじゃありませんか。とにかくこの分らなづくめの謎は、小六爺さんの口一つにかかっているんですが、ひょっとして、一座が割れるようなことでも起りゃしないかと思うと、うっかり口には出せず、まるで身体中の毛が、一本一本逆立つような思いをしながら、今にどこからか里虹が飛び出して来て、わっしと久米八との関係を、喚き立てるんじゃないかと思うと、もう居ても立ってもいられず、そうなると、爪の先から血の音が聴えてきたり、手足が冷たいくせに、たぎったような血が脳天に上って行くのが判るんですよ」
その時儀右衛門が苦しくなって中止したように、それはなんとも云えぬ、不気味な表象だった。
夷岐戸島の秘密、クイロスの絵画、里虹の生死──と次々に鬱積していったものが、いつとなく土台の底深くを、じりじりと蝕んでいて、やがては思いもつかぬ、自壊作用となって現われるのではないだろうか。
それでなくてさえ、大地が暗く、夢中をさ迷い歩くような感じがして、暗中に差し招く、隠密の手をはっきりと意識しているばかりではなく、こうも眩い白昼においてさえ、彼を襲う、奇怪な恐怖を制し得なかったのである。
法水は、しばらく相手の顔を凝っと眺めていたが、こうして白昼夢を追い、狂いの道程を辿りつつある儀右衛門を見ると、もはや放ってはおけなくなってしまったようであった。
「ところで、友田屋、これだけは、どうあっても口にしまいと、決心していたんだがね、実を云うと、君と久米八は、実の兄妹ではないのだよ。僕は君の身体から、あの怖ろしい爪を引き剥がしてやろう」
と瞬間眩暈いをしたような儀右衛門を、にこりと見て、
「君は、夷岐戸島の秘密を、それからそれへと曝いていったね。しかし、まだ一つだけ、君の眼に止まらなかった井戸があるのだよ。では、その蓋をあけて、君が発見した、双生児の特徴に加えるものを、覗かせてあげよう。
君は、クイロスの画の中で、たった一ヶ所だけ見逃した部分がある」
なに、クイロスの画に──というような儀右衛門の眼に、法水は再び微笑った。
「と云うのは、一方が苦しんでいると、片方の子が、それと同じような表情をして、右胸を押えているということだ。実を云うと、それが何あろう、双体畸形の特徴なんだよ。
十九世紀の末頃だが、有名なシャン・エンの暹羅兄弟──それが、一八七二年に死んだときのことだった。その時、パウル・ガリンスキーという人が、解剖の結果を発表して、その中に内臓転錯症のことが記されてあるのだ。つまり胸の剣状突起のところで癒着いている、右側の一人には、心臓は右に、その他ありとあらゆる臓器が、左側のと反対の位置にあるというのだ。そして、その現象は、シュワルベ、サンチレール、フェルスター、レーシェルなどの、有名な畸形学者がいっせいに容認するところとなって、双体畸形の右側に位するものは、一様に心臓が、右にあるということが判ったのだ。
ねえ友田屋、君は双体畸形が、健康も感覚も情緒も、共通なのを知っているかね。そして、一方が軽い病気をしてさえも、片方が、不快な感覚を起すということも──。つまり、あの絵の中で、表情が同一なことと、片方の小児が右胸を押えているということが、クイロス教授の物云う表象だったのだよ。しかも、二卵性の男女双子に、暹羅兄弟が全然ありえないということを知ったら、はっきりと君は、悪夢から醒めるだろうね。
つまり君はローザとジョーゼ姉妹のように、クイロス教授の手術で分離したのだよ。ハハハハそんなに方々見廻したって、どこに嬰児の時の傷が残っているもんか」
暹羅兄弟──それが片輪と名づけられる中で、もっとも地獄的な一つだとすれば、当然里虹は、母の人魚とともに、この世から葬らねばならなかったであろう。
儀右衛門は、その意外な名を聴くと、さらに新しい、一つの魔夢の中に入ったような気がした。けれども、そうして現実の恐怖から、はっきり截ち切られてしまうと、それまで覚えもしなかった、一つの疑惑が頭をもたげてきた。
と云うのは、法水の推断によって、久米八が兄妹でないということになると、当然双体畸形の相手を、村次郎か逢痴かのいずれかに求めねばならず、はては、二人のいずれがそうであるか、またその結合のし方も、胸かそれとも、背中合せの薦骨のあたりではないか──とまで考えるようになってしまった。
まったく、その二つのものは、果しなく絡み合って、結局は見透しのつかない、雲層の中に埋れてしまうのであるが、またそうなって、双体畸形の片方が、もし逢痴である場合を考えると、彼の恋情にも、なんとなく怖れが出てくるのだった。
と云うのは、いかにプラトニックであるとはいえ、それは精神的近親相姦にほかならないからだ。
しかし、いずれ彼の疑惑のすべては、小六の口によって解決されるであろう──あの夷岐戸島ただ一人の生残者は、今に何もかも話してくれるにちがいない。まだまだ、儀右衛門の心の中では、双体畸形のことはもちろん半信半疑であり、わけても、逢痴に対する愛着が、そうでなかれかしと秘かに祈るのであった。
ところが、その日のうちに、片身の本体が明らかにされたと云うのは、そうして対座中、どうしたことか、法水が聴耳を立てはじめたからである。
それはどこかから、チャリンチャリンと楽玻璃のように、一定の節奏をもって、快い玻璃の音が響いてくるのであった。
「ねえ友田屋、どうやらこれから、小道具部屋に行かなけりゃならんよ。たしか彼処には、『唐人殺し』に使う、玻璃房の燈籠が下がっていたっけね。彼処で誰か、首を縊っているんだよ。ほら見給え。少し休んで、またやりはじめるだろう。また少し休んで……」
儀右衛門は、それを聴いてハッと顔色を変えたけれども、法水の透視的神経は、黒死館殺人事件一つでさえも、優に十五を数えるではないか。
やがて、横合の廊下まで来ると、そこで儀右衛門は、釘付けされたように立ちどまってしまった。
なぜなら、廊下に向けて開かれてある、硝子戸越しに、ダラリと下った、小六の両手が見えたからである。
そして、口は嚥み込む、何ものかをもの欲しげに、ゲッとばかり開かれているのだ──小六は、左右に玻璃燈籠を吊した、紐に縄をかけて、無残な縊死を遂げているのであった。
「ねえ先生、いったい全体、小六は自分から死のうとしたのでしょうか、それとも、誰かに吊されたのでしょうか」
儀右衛門は、この老侏儒の身体を抱き下しながら、われともなくそう云った。
しかしそれは、まばらな歯並が覗いている、紫色の唇ではなかった。まったく、彼の思考を読み取ることができる、不思議な力でもないのなら、こうも符合したように、小六の死が速急に現われる道理がないのである──ただ一人、それも、あの怖ろしい秘密を解くことができる、ただ一人の男が死んでしまった……。
そうして、彼には、この無残劇の深さがとうてい測りえなかったのであるが、そのうち、思いがけない喜びが訪れてきた。
と云うのは、小六にまだ、体温が残っているのを発見したことで、それから総掛りの人工呼吸の結果、この老侏儒はようやく蘇生することができた。
すると、なんとしたことかむっくと立ち上って、胸から出る息が、苦しげに響いた。
「ふ、双生児め。あれ、彼処を通る、あいつがそうなんだ。胸と胸を、くっつき合わせやがって」
と汚ならしい、獣物に触れるような血相で、顫えつつ前方を指差すのであったが、そうしてから法水の腕に凭れて、今度も異様な言葉を呟くのだった。
「ねえお前さん、皆んなが寄ってたかって、わっしのことを小さいと云うがね。しかし、真実小さく見えるなあ、わっしじゃねえ、彼処にいる為十郎なんだよ。ええ、侏儒奴が……」
そのとたん一同の視線が、おりから湯上りの為十郎に注がれたが、その老人は、軽く嘲ら笑ったのみで、深い皺をひょうきんな手つきで引っ張り上げた。
「わっしが、侏儒だって、冗談じゃねえ。小六さんは、まだ正気に帰らねえんですよ。それよりか、豊竹屋さん(逢痴の事)が双生児とは、そりゃまた、どうしたってことなんです」
「なあ、私が双生児なんですって。でももっとも、いま小六さんの前を通ったのは、私だけなんですけど……」
と逢痴は、こころもち臆したようであったが、それは何もかも、女になりきった、恥らいのようにも見えた。
彼は法水に気づいて、静かに会釈したが、
「ですけど先生、いったい小六さんは、自分から首を縊ったのでしょうか、それとも、誰かほかに……」
と逢痴が、ズバリと云いきったのは、この場合けっして不自然な質問ではなかった。
と云うのは、小六の襟首に、一つ胡桃大の結節の痕が現われていて、どうやらそれが、他殺を匂わせるのだった。
しかし、一方小六を、どんなにか賺めすかしても、彼は顫くのみで、一言も口にはしないのである。
法水も、困りきったような顔をして、
「なるほど、豊竹屋の云うとおりなんだよ。現に、ステイフェンの『証拠蒐集綱領』を見ても、たいていの場合頸筋の結節は、紐が長くて、縊死者が廻転した場合に起るものなんだ。けれども、稀に犯人の自白などで、例外な場合が起ることはあるがね」
と小六が、昏々と眠りはじめたのを見ると、彼は儀右衛門の耳に口を寄せた。
「自分が、首を縊らねばならぬ原因も云われないし、また、加害者の名も口に出せないとしたら、この一座の暗闘状態は、案外深刻なのかもしれんよ。きっと、僕らには思いもつかないような、底のまた底があるにちがいないんだ。
ところで、参考のために、僕がどうして、この老人の縊首を発見したか、説明しておこう。
これは、簡単な波動の原理なんだが、例えば、池に二つ石を投げ込むと、同じように波紋を起すだろう。ところが、その中間に、より大きな石を投げ入れると、もしその波紋の方向が、同じな場合には、前の二つが消えてしまうんだよ。つまり、この二つの玻璃房は、最初老人の首が掛ったときには振動するが、それから撚目が、行き詰りまでゆく間には、しだいに衰えて、極限に達すると静止するのだ。また、次に解けていって、最初の状態に戻ると、再び力が加わって振動を始めるのだ。その節奏から、僕は異常な啓示をうけたのだったよ」
事実、一座には、刻々と高まってゆくような、妙に不安定な空気があった。それを、法水は仄かに感じただけで、その日は、ほどなく戻ってしまった。
けれども、この日の出来事は、儀右衛門にとると、彼が築き上げた、あらゆる仮説の顛覆を意味するのである。
もし、小六の云うのが真実だったとして、夷岐戸島の侏儒が為十郎だとすれば、この一座を里虹とともに築き上げた彼は、はたして何者なのであろうか。また、風のように現われた為十郎が、真実その侏儒だということになると、その間の消息を、小六は何故に知り尽くしているのであろうか。
しかし、何より儀右衛門を、絶望の淵深くに叩き込んだのは、いよいよ小六によって、逢痴が双体畸形の片割れだというばかりでなく、胸と胸とが癒着している、いわゆる剣状突起癒合であることが、判明したからである。
そうなると、逢痴に対する愛着が、まったく厭わしいものになってしまって、再び彼は、昏迷の泥沼へ深く沈みゆくのであった。
それは、往々に壮年者が見る、忌わしい艶夢のようなものであった。と云うのは、近頃ことに親しい久米八と逢痴の間を考えると、時として彼の眼前に、異様な白昼夢が出現するのだった。
一人の女と一人の女形、その美しい円味、匂いこぼれるような媚めかしさ、悩ましさはともかくとして、おりふし「青楼十二時」でもひもどいて、辰の刻の画面に打衝かると、ハタと彼は、その折帖を伏せてしまうのだった。もし、三人の夢が、幻像を画いて通い合うとすれば、自分が帰った後の蒲団には、舞台姿の逢痴が横になっていて、その側から掻巻をかかげ、入り込もうとしている久米八は、さぞ自分が残した、温かみに眉を顰めることであろう。
そうでなくてさえ儀右衛門は、そうと知ってからというもの、双体畸形特有の、奇異な心理に翻弄されはじめた。
それは、永劫に解けぬ循環論であった。
双体畸形の二人は、一人でも二人でもなく、生命は二つのようでもあるが必ずしもそうではない。
そうなると、時計の振幅がだんだんに狭められてゆくように、逢痴に対する愛着も、つまるところは、自分自身を恋するように思われてきた。そして、はては四次元が三次元に、また二次元にと、ついには外界のすべてが、自分自身の中へ沈潜してゆくのではないかと、顫かれたのである。
しかし、それは明らかに、狂気の前兆である。
儀右衛門は、その危険な囁きから遁れようとして、最初の夜のことを想い出した。そして、何より一応は、現場の瀬踏みをしなくてはならぬと考えた。
と云うのは、あの時小六と逢痴との間は、玻璃の房に隔てられていて、たしかに小六は、その三稜鏡のため、二重に見えたのではないか──と考えられたからだ。
しかし、今度は案に相違して、その玻璃房は、二重屈折の三稜鏡だった。
したがって逢痴の姿が、二重に映ろう道理とてはないのである。
こうして、否定と肯定とが背中合せして、紛乱の渦が、いよいよ波紋を拡げているうちに、いよいよこの一座は、「四谷怪談」をひっさげ東都初登場となった。そして、河原崎座の初日に当って、まったく無残絵か因果絵でなくては見ることのできない、血みどろの悲劇が捲き起されたのであった。
大南北の「東海道四谷怪談」を、原本どおり演出するというので、たださえ狭苦しい場末の河原崎座は、割れんばかりの大入だった。
狂言数も進んで、いよいよ二番目の「四谷怪談」に入った。
その二幕目伊右衛門の浪宅、いわゆる髪梳きの場である。
お岩は逢痴、宅悦は小六。舞台は、上手障子内に蚊帳を吊り、六枚屏風を立てて、一体の作りが浪人住居の体。演技はすでに幕切れに近かった。
お岩 ヤヤ着物の色合、つむりの様子。こりゃ、これ、ほんまに妾が面か、このような悪女の顔に。なんで、まあ、こりゃ、妾かいの妾かいの。妾がほんまに顔かいのう。
と髪は解け、垢じみた肌襦袢に包まれて、全身から放っていそうな、異様な臭いを振り撒きながら、産後のお岩は、鏡を手に持ち、見るも無残な変貌を、物怖ろしげに見入るのであった。
それは、おどろ怖ましい色であり、靄であって、その物凄まじいおののきには、自分の心臓すらも、観客は見出せないほどであった。
そして、宅悦との応答があって、髪梳き道具が持ち出されると、お岩は櫛を手に取り、思い入れよろしくの後に、
お岩 母の遺品のこの櫛も、妾が死んだら、どうぞ妹へ。アア、さはさりながらお遺品の、せめて櫛の歯を通し、もつれし髪を。オオ、そうじゃ、
そうして、櫛で梳くと、はじめは少し、二度目は一つかみほどの、もつれ毛がからみ落ちて、そうした跡は、光りもせぬ不気味な白地。
そこからはまるで、絹ででも濾したかのよう、粟粒ほどの血の滲み。
やがては、水に拡がる油のよう、一筋二筋と糸を引きはじめ、吃驚したお岩が櫛を捨て、右手に髪をひん掴むと、それは内臓の分泌を、滓までも絞り抜くかと思われるような怖ろしさだった。
ばらりと抜けた一つかみの毛を、両手に握りしめて、恨めしげにキュッと捻って、すううと糸を引いた一筋の紅は、色でもなく血でもなく、それは暗い煙りのように見えた。
お岩 今をも知れぬこの岩が、死なばまさしく、その娘。祝言さするは、これ眼前。ただ、恨めしきは伊右衛門殿。喜兵衛一家の者ども、ナニ、安穏に置くべきや。思えば思えば、エエ恨めしい。
と、月と葭を描いた衝立の蔭から、よろよろと蹌踉き上り、止めようとする宅悦の襟首をひっ掴んで、逆体に引き据え、上になったお岩の生際から一溜の生血、どろどろと宅悦の顔にかかるのが、幕切の見得。
ところが、そうした陰惨な色どりが、未だに消えぬ観客の耳に、つんざくような叫喚が、幕の背後から聴えてきた。
それは、衝立の蔭で、夷岐戸島唯一の生残者と目され、先には不可解な縊死を見せた宅悦の小六が、今度こそは、白眼を剥き出し手足を縮めて、それはあえなくも息が絶えていたからであった。
この意外な突発事件は、その日の興行を、髪梳き場だけで中止させてしまった。
そして、観衆が立ち去った後は、広い空間を、侘びしげな空気が揺れていてその中に、二、三蟻のように蠢いて見えるものがあった。
それが、法水のほか、四、五人の検屍官一行だったのである。
ところが、不審なことには、屍体にはどこぞといい、他殺の痕跡がないのだった。中毒と覚しい痕もなければ、皺の深みに隠れている、針先ほどの傷もなく、両眼も睜いてはいるが、活気なく物懶そうに濁っている。
そこで検屍官は、小六の屍体に自然死を推定した。
「ところで法水さん、聴けばこの一座では、『四谷怪談』がかつて一度も、上演されたことがないと云うじゃありませんか。そこに、この老人の衝撃死の原因があったのですよ。御覧のとおり、胸腺淋巴体質というやつは、衝撃には恐ろしく、鋭敏ですからな。もっとも、衝立の蔭で、観客に見えない場所で死んだのですから、疑惑と云えば、その点が多少どうかとも思われますがね」
法水は、検屍官の言を聴くともなく、傍らにあった、お岩の半面仮髪を弄っていた。
それは、右眼の下のところまで被さるもので、髢を解いて一本ずつ針に通し、それを羽二重に植え付けたものである。
つまり、そこに髪梳きの、技巧があるというわけだが…その時は仮髪師為十郎の趣向からして、幕切の見得の際には照明を暗くさせ、眼だけを白く抜いて、真赤に滲み出る毒血の凄みを、内部に塗った、燐で浮き出させる仕掛けにしたのである。そしてまた、これは後日のことであったが、そうして宅悦の顔に滴り落ちた血糊の紅には、何一つ検出されたものはなかったのであった。
法水は、その仮髪を置くと、はじめて思い出したように検屍官を見て、
「なるほど、衝撃死ですか。しかし、衝撃と云っても、貴方はその対照が、何ものであるか、御存知ないのでしょう。ハハハハ、衝撃をうけて風のようにこの世を去った──ただそれだけでは、少しでも、秘密の感受性に強いと、その人間に、貴方は嗤われますぜ。たぶん貴方は、幕切の際に、照明を暗くしたことは御存知でしょうが、その時、この老人の心動を止めたものがあったのですよ」
と、かたわらの床から、取り上げたものを見て、一同は少なからず驚かされた。
それは、お岩の変貌を写す鏡で、今どきとうてい見ることのできない、古風な長柄の鉄鏡だった。そして、裏面には、六つ手薊の模様が、透し彫りになっているのだ。
ところが、法水に表を返されて、一同はあっと叫んだ。
と云うのは、その鏡面に、薄く滲み出たかのごとく、紅で、五本の指痕が印されてあったからである。
「ところで、こういう昔の鉄鏡に、一種不思議な現象があるのを、御存知でしょうか。それは、表面何事もない鏡でも、一度光を当てると、なんともいえない不思議な模様が、前方に映ることです。しかし、その正体というのは、鏡の裏面にある浮彫りなんですよ。それは、最初鏡を磨く際に、模様のある低い部分が、一端は凹むのですけど、やがて日を経るにつれ盛り上ってきて、結局、不思議な像を反射するようになるのです。むろんこの鏡も、六つ手薊をそのまま反射するのですが、ここに問題なのは、表面に着いている五本の指痕なんです。偶然かは知りませんが、それが六つある、刺葉の合間合間に符合しているのです。ですから、けっこう暗くなると、お岩の左頬に何ものか、映らなくてはなりますまい。尖った、十一本の刺を持った、手掌形をしたものと云えば、それはいったい何でしょうかな」
そう云って、いちいち法水は、座員の顔を見渡していたが、誰もかも、凍り付いたように血の気を失っていた。
と云うのは、もはや贅言を費やすまでもなく、それは、はっきりとあの魔の衣裳──いつぞや儀右衛門に示されたところの、人魚の尾鰭形をした、図紋だったのである。
その意外な出現が、小六に衝撃を与え、彼の心動を止めたに相違ないのであるが、そうなると、その指痕の主は何者であるか、疑問はそこに残されてしまった。しかも、それには一つの特徴があって、右手であるばかりか、食指と無名指とがほとんど同じ高さであり、拇指はやや横向いていて、それと、小指との識別は不可能なのであった。
しかし、それから座員を去らしめて綿密な調査を行なったのだが、ついにそれが逢痴に決定されてしまった。
「ところで友田屋」
法水は帰りがけに、儀右衛門を訪ねて、
「むろん、僕の推断を刑法的に見たら、おそらく、なんの価値もあるまいがね。しかし、あながち夢想でもないのだよ。と云うのは、小道具掛りの中に、たしか今里銀五郎とかいった、恰腹のいい、顔中切り傷だらけの男がいたっけね。その男をはじめ、その時、奈落の切り穴の下にいた連中が、全部口を揃えて、幕切の際小六が、「ウーム、逢痴め、逢痴め、」と叫んだ声を、耳にしたと云うのだよ。けれども僕には、そんな暗合の魅力に陶酔していると、今にとんだことになるぞ──というような予感もあるのだがね」
その夜、儀右衛門には怖ろしい夜が訪れた。
と云うのは、この事件を機会にして、再び、彼を悩ましつづける、神経の蠢動が起りはじめたからだ。
それは、また例の鏡像で、はからずもその特徴を、自分の左手に発見したのであった。彼の左手は、逢痴の右手と同じに、やはり二つの指の高さが同じなので、もし拇指と小指の判別が、真実つかない場合には、決して決して、犯人が逢痴であるとは云えなくなるのだ。
それでなくてさえも、近頃は頻々と白昼夢を経験したり、時折はまた、茫っと意識から遠ざかるような場合もあるので、臆せまいと思い凝っと瞼を閉じていても、あの怖ろしさだけは、とうてい拭い去ることができないのであった、しかし一方にはまた、里虹の生死のことが考えられてきて、何かこの一座の中に、偉大なもの、怖ろしいもの、超自然的なものがあるのではないか。また、それが、妙に自分とばかり通い合う、奇異な存在ではないかとも考えられてきた。
ところが、その翌日、前夜のうち逢痴に対する令状が発行されたとみえ、閉場を待つ私服の群が、観衆の中で鋭い眼を光らせていた。
いまや舞台は、三幕目砂村隠亡堀の場。
背後は高足の土手、上手に土橋、その横には水門、土手の下は腐った枯蘆、干潟の体である。干潟の前方は、一面の本水で、それが花道の切幕際にまで続き、すべてが、先代右団次そっくりの演出であった。
伊右衛門 よしなき秋山うせたばっかり、口ふさぎに大事の墨附、あいつに渡してこの身の旧悪。ハテ要らざるところへうせずとよいに南無三暮れたな。どりゃ、竿を上げようか。
しかし、伊右衛門は、まだ未練げに、凝っと浮きを見詰めていると、やがて髪毛がかかり、次に引き上げた櫛の歯から、一筋二筋と、もつれ毛を取り去る、指のしなだれ、その蒼白さ。
時刻も黄昏、所は十万坪隠亡堀、すべてが陰の極みである。
すると、おどろ怖ましい薄ドロにつれて、下手から、菰をかぶった一枚の杉戸が流れ寄る。
端には一塊の腐れ縄、そこに、蛙がひょんと跳んで、凝っと動かないのだ。
伊右衛門思わず仰天して、
やや、覚えの杉戸は。
と、戸板にかかった針先をとろうとし、つるりと滑った途端に、菰が摺り落ちて、皮も萎え血もしこり、肉脱した岩の死骸が、ぬるっとばかりに現われた。
しかしその時、観客の駭きはともかくとして、伊右衛門に扮した、山村儀右衛門が、どうしたことか、どかっと尻もちを突いた。
と云うのは、なんとそのお岩が後向きであって、ただ守り袋をさしつける人形の作り手のみが、ひょいと不器用な、動きかたをしたにすぎなかった。
伊右衛門 まだ浮ばぬな。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。このまま川へ突出したら、鳶か鴉の。業が尽きたら、仏になれ。
と、戸板を蹴ると、今度は裏に返り、藻をばらりと被った小仏小平が、「お主の難病、薬下され」と、片手を差し出すかと思いのほか、それも背後を向いているのだった。
その瞬間儀右衛門は、全身の血が、まるで逆流せんばかりの思い、いまや一身に、世界中の嘲りをうけているような気がした。
と云うのは、舞台こそ異なれお岩と小平の向き合せは、かつて胸を癒着ていた、彼ら双体畸形のそれではないか。
しかし、儀右衛門は気力を振い起して、
伊右衛門 またも死霊の。
と、抜打ちに死骸に切りつけると、大ドロあって、浪幕の間より、代りの戸板が差し出されて、骸骨を載せたまま、本水の中を花道指して流れ行くのであった。
けれども、その時儀右衛門は、塑像のように動かなくなり、釣竿を腕に支えたまま凝っと戸板の上を見詰めていた。
もはや彼は、奔馬のような脈を感じ、錯覚さえも生じて、蘆も土橋も水も何もかも、キラキラした、陽炎の中に消え去る思いがした。と云うのは、いかなる魔の所業であろうか、戸板の上の骸骨には、肢首が括り合わされていて、それが人魚を象どる、あの図紋のように感じられたからである。
しかし、そのうち水門が開かれて、滝流しの浴衣を着た与茂七が現われると、舞台は陰惨の極から、華麗の頂辺に飛び上り、まさに南北特有の生世話だんまり、あのおどろおどろしい声や、蒼白い顔や、引き包まんばかりの物影などは、とうに昔の夢と化して、どこかへ飛び去ってしまうのだった。
ところが、そのだんまりの真最中、板戸が進み行くにつれて、なにか金色に輝いた脂肪のようなものが、水面をじわりじわりと拡がって行くのだった。そうして花道を行く間に、だんだんと右に傾いて行き、ようやく切幕の下に達したとき周囲の観客はつんざくような叫び声を上げた。
見ると、戸板がくるりと返って、そこには、お岩の衣裳を着、咽喉に無残な孔を開いた花桐逢痴が、ぬうと、藻の中から顔を突き出しているのだった。
こうして、観衆の真唯中で、小六殺しの推定犯人逢痴は、無残な死体を曝したのである。
死体には一面に太い襞が盛り上っていて、肋骨が浮き上り、傷は左横から、刃様のもので頸動脈が貫かれていた。
しかし、こうして死に、硬くなって、永久動くことのない身体のいろいろな部分が、法水の眼には、異常な意味を持ってきた。彼は何度となく水中を透し見たり、浮んでいる作り藻を絞ったりしていたが、そうして滴り落ちる蒼黒い水に、明らかな失望の色を泛べるのだった。
彼は、傍らの儀右衛門を振り向いて、
「どうだね友田屋、君は気がつかんかね。こりゃ、とてもひどい出血なんだぜ。ところが、浮いているのは、血漿や脂肪だけで、肝腎要の血が、この水の中にどうしても見出せないのだ。屍体には、これほど明らかな羸痩が現われていて、そのくせ、血がいったいどこへ行ってしまったのだろうか。藍で染めた水の中に、赤いものがあれば黝ずんで見えるのだから、何より色を見れば、一目瞭然じゃないか。すると友田屋、これで逢痴の死が、戸板の中で行われたのでないという事が分るだろうね」
そうして、執念く作り藻を取り上げては、キュッと捻り、したたる水の色を、貪るように眺めているその光景には、また髪梳きの場が聯想されてきて、それは「玻璃の光り」という、下座の独吟でも欲しいほどの物凄さだった。
しかし、水中に出血がないという事は、一方において、殺人現場を舞台以外に局限してしまった。そうなると、当然裏向きお岩の疑問が起ってきて、幸いだんまりの場面の暗さを機に、あれが誰かの一人三役ではないかとの疑いも起ってくるのだった。
しかし、そうしているうちに、舞台裏の調査が終って、実に驚くべき、報告がもたらされてきた。
と云うのは、座内を隅々まで探したのだったが、一滴の血さえ発見されないばかりでなく、誰しもが、格闘の物音も聴かずと云い、ただ逢痴の部屋から平素使う沃度の注射器を、拾い上げて来たのみであった。
そうなってみると、出血の失踪は、実に驚嘆すべき奇跡となり、早くも法水の顔には、ただならぬ困惑の色が現われた。
したがって奈落の調査が、慌しく行われることになったのである。
この座の奈落には、小芝居特有の色が現われていて、天井の低い、すべてが、だんだんと朽ちて行く、骨のように黝ずんでいた。
そして、白っちゃけた壁や、中央にある轆轤には「四谷怪談」に使う漏斗の幽霊衣や、仏壇返しや、提灯の仕掛などが立て掛けてあって、何もかも、陰惨な沼水そのもののような代物ばかりだった。
しかし、法水は、そこにいる村次郎の口から、戸板返しの技巧を聴くことができた。
「つまりなんでさあ、本水口に使うのと、お岩を入れるのと、杉戸が二枚いるんですよ。そして、最初は下手の方から、菰を被せたのを流して来るんですが、さて伊右衛門の前に来ると、それを浪幕の陰から、手際よく引っ張り込むんです。そして今度は、役者の入っている方を、みんなでかつぎ上げて、きっかけと同時に、ぬうと突き出すという寸法なんですよ。ところが御覧のとおり、浪幕があるものですから、奈落はせいぜい二燭の電球ぐらいで、人の顔なんぞ、てんで見分けがつくもんですか。つまり、そんな具合で、間の悪い時だと、杉戸の所在が分らなくなるものですから、こうして同じ孔をあけたやつを二つ作っておくのです。ところで、この杉戸ですが、御覧のとおり、少し幅広に作られてあるでしょう。そして、間に役者が入って孔から顔だけを、突き出すんですよ。なあに他愛のねえもんで、外側は括り付けの衣裳なんでさあ。ですが、今日はなんとも不思議なことで、誰か取り違えて押し込んだのかも知れませんが、豊竹屋が後向きに入ってしまったんです。なんですって、それが豊竹屋じゃねえって──とうに殺されていたっておっしゃるんですか。じょ、冗談じゃねえ、わっしらはちゃんと、台詞までも、聴いているんですからね」
「なに、逢痴の台詞を聴いたって──」
法水は、その一度ですっかり顔色を失ってしまった。
「そうですとも、聴いたのはわっしばかりじゃねえ、みんながそうでさあ。なあ、銀五郎──」
と傍らにいる、顔中傷だらけの小道具方を見て、村次郎は同意を求めるように云った。
「なにしろ、最初本づりのきっかけで、入って来たのも、豊竹屋なんですよ。それからわっしらが、総掛りで浪衣を着て、杉戸を差し上げているうちに、何を見たのか為十郎が、アッ久米八さんが──と叫んだものです。ですからわっしは聴えてはならぬと、為十郎の口を塞ぎましたが、それからすぐとお岩の台詞になり、小仏小平がすんで、ようやく杉戸を下しましたが、それからが、息を次ぐ暇もないほどの早業なんです。前に引き入れておいた、もう一つの杉戸に、骸骨を引っ掛けて、それを本水の中に、押し出したのですよ。ええ、見ましたとも。むろんその前に、滝流しの浴衣に引き抜いて、飛び出した豊竹屋を見ましたとも。ですから、わっしには、どうして豊竹屋が──ねえ先生、現在眼の前に、自分の死骸を眺めながらだんまりを演るなんて──」
村次郎は、咽喉をゴクゴク鳴らせて、息を出すのも、苦しげになってきた。
しかし、そうしてこの事件は、紛糾混乱の絶頂にせり上ってしまったのである。
現在眼の前には、二枚の杉戸が立てかけられているのだけれど、それとて一様に、小仏小平の衣裳がなく、同じように水に濡れていて、しかもその衣装は、眼前の床に投げ捨てられているではないか。すると、もっとも合理的な解釈が、不可能になってしまって、犯人は暗さに乗じ、お岩・小平・与茂七と、三段早変りを演ってのけたのがそうであり、逢痴はそれ以前、幕間にでも殺されていて、屍体を隠した杉戸が、それとも知らず、水中に押し出されたのではないか。
と、そうも思われたけれども、何より楔のように打ち込まれた、逢痴の声と血潮の失踪とが、それを根底から否定してしまうのだった。
そして、裏向きお岩の謎は、遠く遠く雲層の彼方に没し去ってしまったのである。
ところが、その翌日、法水が河原崎座を訪れた時は、ちょうど四幕目の終り、これから「蛇山の庵室」に、かかろうとする際のことであった。
儀右衛門は、法水の顔を見ると、顫きながらも、待ち兼ねたように切り出した。
「実は先生、ゆうべ一晩で、わっしは十年も、年老ったような気がしましたよ。と云うのは、村次郎が云った逢痴の台詞のことですが、そう云えばなんとなく、嗄れたような声を、聴いたような気もするのです。しかし、問題というのは、その後でして、実は昨夜、わっしが使った刀を抜いて見たのですが、それには薄っすらと脂肪が浮き出ているではありませんか。あの時わっしは、あの向き合わせを見ると、思わずそれに、暹羅兄弟が聯想されて、赭っとなりました。そして、たぶん切りつける所作の拍子に、逢痴の咽喉を刺したのかも知れませんよ。けれどもそうなると、わっしを踊らせた人形師が、ぜひともここで、一人必要になってくるのです。それは、杉戸入りの際に、逢痴を裏向きに押し込んだ人物で、たしかあの時、奈落にいた六人の一人に違いないのです。先生、わっしはなんという因果でしょうか、実の弟を殺してしまったのですよ」
法水は、しばらく口を噤んで、何事も云わなかったが、やがて全身の気力が、眼の中に移ったかと思われた。
「だが友田屋、それを僕に云わせると、けっして弟殺しとは云えないのだよ。実は、今朝の解剖で、僕は動かせぬ確証を掴んできた。逢痴には、暹羅兄弟特有の、臓器転錯症がなかったのだよ。すると、三引く二は一じゃないか。君の片身は、村次郎なんだ。しかも、その二人が、里虹の子であるという証拠は、あの、人魚の尾鰭を象どった図紋なんだよ。実はあれが、竜鋤の形で、トラケーネン血種という、高貴な馬に捺す烙印だったのだ。つまりクイロス教授は、あの画の中で、双体畸形こそ、嵯峨家の血系であると暗示したのだ。だが、それはそれとしても、なんだか僕には、逢痴殺しよりも先に、君の親殺しを、訊ねねばならぬ義務があると思うのだよ。ねえ、そうだろう、里虹は君が殺したんだっけね」
その瞬間、儀右衛門は化石したようになって、それは永いこと、姿勢を改めなかったのである。しかし、法水は静かに言葉を次いだ。
「いつぞや、君に里虹が失踪した時刻を、訊ねたことがあったっけね。すると君は、風が止んだのが午前三時で、騒ぎ出したのは、たしか六時十五分前頃でしょう──と云った。しかし、後で調べてみると、風が止んだ時刻は、すでに五時近かった。そこで僕は、その偽りが、何に原因しているのか考えはじめたのだが、ふと思いついたのは、三時も五時四十五分も、それぞれ時計の盤面では、直角をなしていてしかもそれが、正午の十二時を軸に廻転しているという事だ。ねえ友田屋、類似聯想たるや、実に正確な精神化学なんだぜ。そして、正午という一語から、昇汞という解答を発見すると、僕はその錠剤の不足を、薬屋の販売台帳から見つけ出したのだ。しかし、それから里虹の屍体を、埋めたか、河に投じたかは問わないにしても、人魚の嘆きを、父に報いた心理だけには同情できるよ。それを、フロイド的に云ったら、いっぷう変った、エディポス複合と云うことができるだろうね」
と、そこで言葉を截ち切って、法水はやや顔色を和らげた。
「しかし、君にしても、おめおめ僕の手を待つとも思われないし、この事件の落着を見ないで死ぬのは、いかにも残念にちがいない。だが、それより何より、はじめての『四谷怪談』を、さぞ君は、終りまで勤めたいだろうね。よろしい。僕は舞台の上で、君に、犯人の声を聴かせてやることにしよう」
そうして儀右衛門が、いよいよ最後の一頁を飾る、劇的な演技がはじまった。
眼は血走り、息は喘いで、台詞の調子はバラバラであるけれども、今か今かと待つ焦らだたしさは、ひとしお末期の伊右衛門に、悽愴な気魄を添えるのだった。
しかし、その頃奈落の中で、法水は、六人を前に何事かを語っていた。
「あるいは君たちの中で、前の座頭の里虹を、知らない者があるかも知れない。けれども、そのむかし里虹と小六とが、或る事情からルソン島へ行かねばならなかったことがあるのだ。その時、クイロスという生理学者が、二人の嬰児に、血液循環の実験をしたのだ。それは、片側の静脈を切って、そこに塩化鉄を置き、反対側の静脈には、フェロシアン・カリウムを注射するのだ。すると、二十何秒か経って、その血液が一順したとき、塩化鉄が溶けて真青な色に変るのだよ。つまり、あの時の逢痴が、意識朦朧としていたというのも、結局は常用の沃度と、フェロシアン加里を掏り変えて置いたからで、また出血が、行衛知れずになったというのも、藍で染めた水のために色が分らなかったからなのだ。さらに小六も、その青血の衝撃をうけて、逢痴逢痴と叫びながら、斃されてしまったのだ。と云うのは、赤い地の中に白い円を置いて、背後から照すとする。それから、しばらく瞶めていると、やがては赤の補色──青色に変ってしまうからだ。つまり、逢痴を思わせたその技巧が、お岩の、半面仮髪の中に、秘められてあったのだよ」
すると、一同の視線が、思わず仮髪師の為十郎に注がれたが、法水の言はたちまちに、その臆測を粉砕してしまった。
「ところが、そうして小六を殺めた人物は、あの時奈落の中で、それは素晴らしい離業を行なったのだ。最初、塩化鉄で練り固めた刃物を使って、頸動脈を刺し貫き、その上二つの杉戸を取り違えさせて、逢痴の死体についている方を、本水の中へ押し出してしまった。それから、浴衣に引き抜いて、与茂七のだんまりを演ったが、その時闇の中で、それは鮮やかに、逢痴の声色を使ったのだよ。しかし、それが誰であるかは、ともかくとして、いずれ僕が、君たち六人の中から指摘して見ることにしよう」
そうして、犯人の所在は局限されたが、ここで再び、形勢は逆転してしまった。村次郎に口を押えられた為十郎だけが、一人安全圏内に止まることになった。しかし、そうしているうちに演技は進んで、すでに蛇山の庵室も終りに近く、伊右衛門が父源四郎に勘当をうけるところで、
伊右衛門 昔気質の偏屈親仁。勘当されたも、やっぱりこれもお岩の死霊か。イヤ、呆れたものだ。
と思い入れのところに、いきなり下の奈落から、声高に叫んだものがあった。
呆れたとは莫迦奴──首が飛んでも、動いてみせるわ。
それは、有名な伊右衛門の台詞であったが、声音と云い、調子と云い、どこか聴き覚えのある声であった。
法水は、それを聴くと同時に、一目散に奈落へ駆けつけたが、扉際でチラリと為十郎の姿を見たかと思うと、内部から唸きの声が洩れてきた。
この事件の悪鬼は、死所を奈落に択んで、多量の青酸を嚥下したのだった。
しかし、村次郎はじめ一座の者は、しばらく放心したように立ち竦んでいた。なぜなら、これまで何の因縁もなかった風来者に、どうして犯人としての、動機があるのであろうか。
「僕は、何よりも先に、悪鬼の再生を告げなけりゃならんよ。里虹は、儀右衛門のために、昇汞で殺されたかと見えたが、そのじつ為十郎となって、未だに生きていたのだ。
と云うのは、阿片食も病い膏肓に入ると、昇汞を混ぜなければ、陶酔ができなくなる。だから、そこへ昇汞をどんな多量に用いても、それはいっこう致死量にはならないのだ。そして、過激な食餌法で脂肪を減らし、過マンガン酸加里の変色法などを用いたので、このとおり不気味な色になってしまった。
しかし、その正体は、ついに小六のために、発見されてしまった。
と云うのは、あの男が怯えて、縊死を計った原因がそれなのだが、あの深々とした皺も、湯か酒で色づいたとき、薄闇の中で見ると、赤みが黝ずんで、変貌の特徴が消え失せてしまうからだ。しかし、一廻り小さく見えるので、あの、侏儒云々の言葉が発せられたのだよ。
つまり、例のプルキンエ現象というやつだね。
それから、云いもせぬ逢痴の台詞が、どうして聴えて来たかということは、少しでも里虹を知る者には、それが得意の、腹話術ではないかと疑われてくる。しかし腹話術には、咽喉変飾、口蓋消音という二大要素があって、口を押えられた彼に、どうして出来よう道理がないではないか。ところが、それ以外にも、胃内の空気を利用する生理的腹話術もあって、もちろん里虹はそれを行なったのだが、なかには、口で喋りながら腹で囃をしたり、二様の言語を、使い分ける達人などもあるそうなんだ。──実はこれこそ不在証明中の不在証明といえるじゃないか」
と、この事件の警畸な内容を、残らず説き終ると同時に、なぜとなく彼は、お岩の半面仮髪に惹かれるのであった。
そして、それを手に持ったとき、天上の切穴から、一筋の血糊が、すうっと糸を引いて落ちた──ああ儀右衛門もか。
しかし、血を血で打ち返す極悪伊右衛門の再生こそ、真実里虹にほかならないであろう。まことに彼は、首は飛んでも、動いて見せたのであるから。
底本:「潜航艇「鷹の城」」現代教養文庫、社会思想社
1977(昭和52)年12月15日初版第1刷発行
底本の親本:「地中海」ラヂオ科学社
1938(昭和13)年9月
初出:「中央公論」中央公論社
1935(昭和10)年8月号
※底本は、物を数える際や地名などに用いる「ヶ」(区点番号5-86)を、大振りにつくっています。
入力:ロクス・ソルス
校正:安里努
2013年4月21日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。